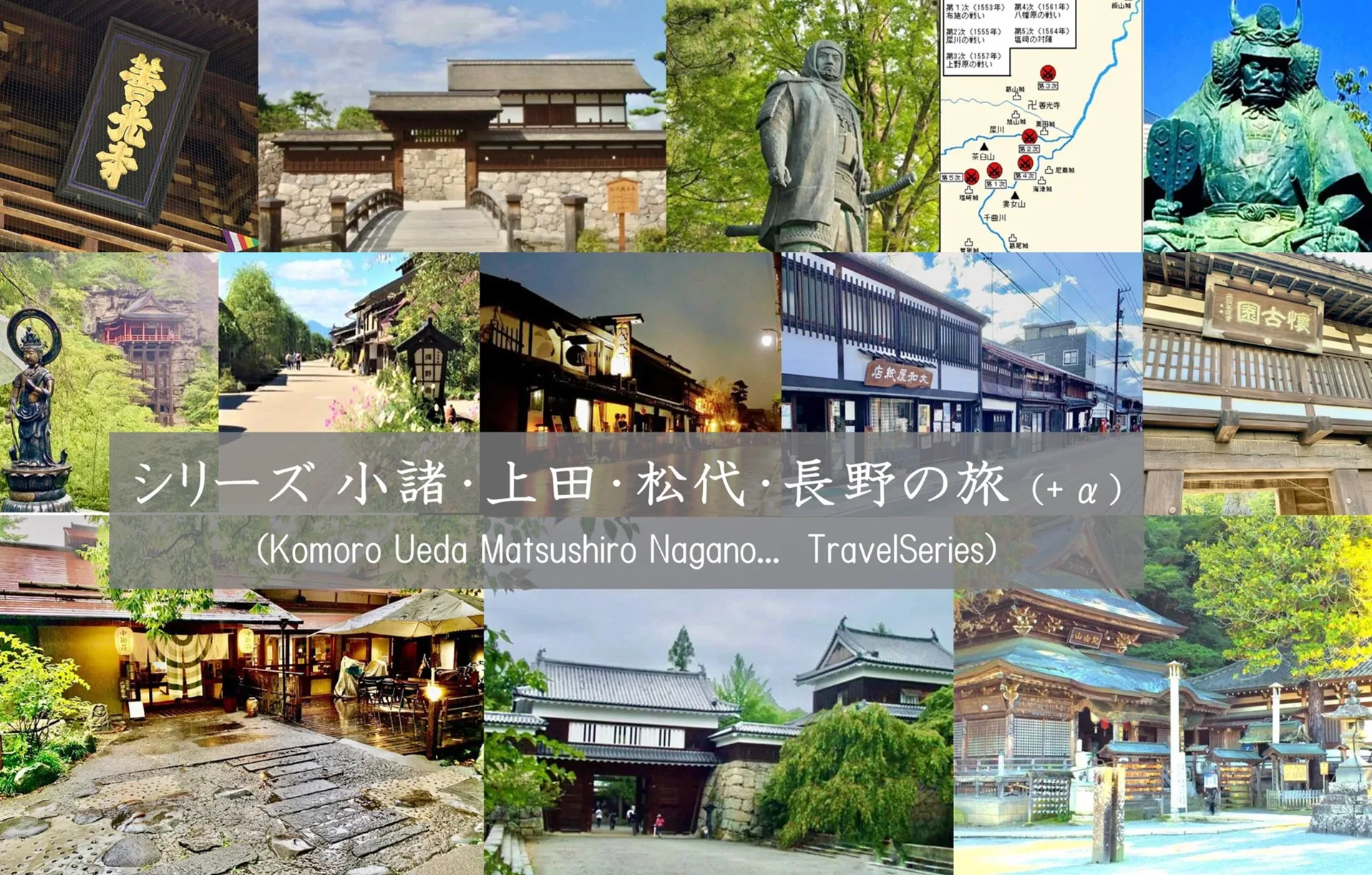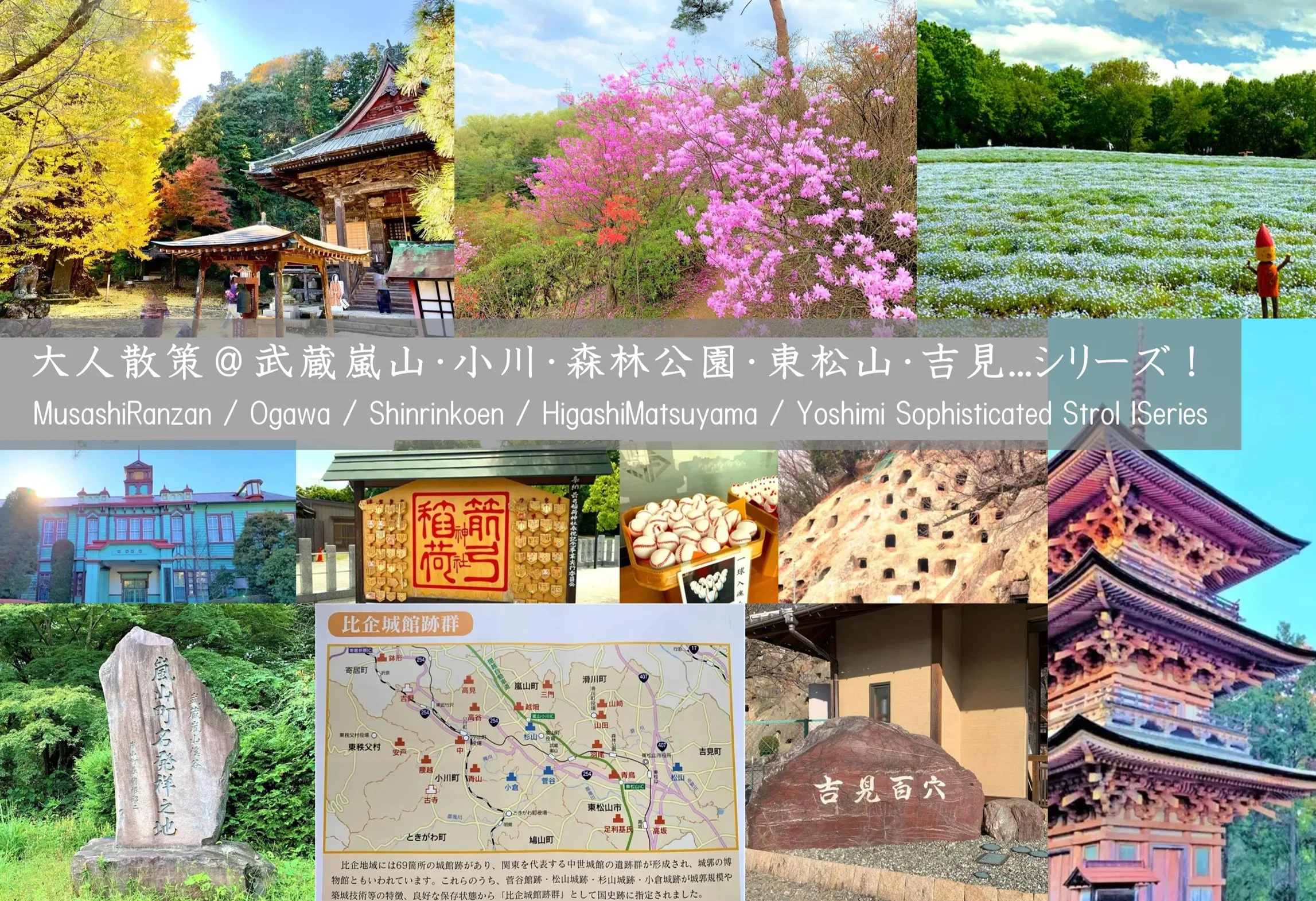玉川上水とは?
江戸時代に多摩川から水を引き、江戸市中へ供給するために築かれた人工水路です。
野火止用水とは?
玉川上水から分水され、埼玉県新座市や志木市へ水を供給した用水路です。
野川の特徴は?
国分寺崖線沿いを流れる川で、湧水や寺社、歴史的遺構が多く見られます。
新河岸川とは?
川越を流れ、江戸期には舟運で栄えた川で、桜並木や神社仏閣が見どころです。
散策の楽しみ方は?
自然や地形を感じつつ、神社仏閣や歴史的スポットを巡ることで文化を体感できます。
こちらのページでは、「別記事で紹介しております、『玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川』等の流れに沿って実行した『水辺の大人散策』情報に付き取りまとめ」をさせて頂きます(各リンクより、それぞれの概要と、具体的なルートや各スポットを記載した大人散策Map(Google My Map にて作成)と共に紹介しておりますので、併せてご参照ください)。
📚本記事で得られる情報📚
✅「玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川」の超概要
✅「玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川」の大人散策における楽しみ方の概要
皆様は、「玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川」等は、ご存じでしょうか? 本ブログ別記事では、「日本三大河川(信濃川・利根川・石狩川)」・「日本三大暴れ川(利根川(坂東太郎)・筑後川(筑紫次郎)・吉野川(四国三郎))」・「日本三大急流(最上川・富士川・球磨川)」と言った、有名所の河川を紹介させて頂きました(個人的な考察や妄想も加えておりますので、別記事ご参照頂ければ幸いです…)。しかし、こちらのページで取り上げさせて頂くのは、「玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川」(今後追加あるかもしれませんが…)。上記記載の河川よりは、有名ではないと思うので、中々ご近所にお住まいの方でない限り、知らない方も多いかもしれませんが、「(個人的には…)人々が生きる為に、”水を確保・活用” してきた痕跡」だと思っている次第です。当たり前の事ですが、『水は、災害をもたらすこともあるので、時には「堤防」を築き、時には「捷水路工事」で直線化し(その痕跡が「三日月湖」である事も…)、”水を制御” してきた歴史』がある一方、『人は水が無いと生きてはいけませんので、河川の流れを変えたり、用水路を築き “水の確保・活用” をしてきた歴史』もある認識です。言い換えると、今回取り上げる「玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川」は、「”水の確保・活用” をしてきた歴史」の側面を持つ “川(用水路)” という事になります。更に申し上げれば、「玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川沿いの大人散策」は、「先人たちが、生きる為に “水の確保・活用” をしてきた痕跡を感じる事がでいる散策」という事になると思っております。




こちらのページでは、そんなその印象を持っている、「玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川」沿いの「大人散策まとめ記事」を記載させて頂きます。すなわち「別記事で紹介しております、『玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川』等の流れに沿って実行した『水辺の大人散策』情報に付き取りまとめ」をさせて頂きます(各リンクより、それぞれの概要と、具体的なルートや各スポットを記載した大人散策Map(Google My Map にて作成)と共に紹介しておりますので、併せてご参照ください)。
【玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川のそれぞれを大人散策!】
上記、「玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川」に付き、個人的に思っている印象を共有させて頂きましたので、こちらの段落では、本ブログ別記事で紹介している記事:「水辺の大人散策シリーズ」のダイジェスト版(超サマリ版?)を共有させて頂きます。それぞれのリンクより、今少し踏み込んだ内容を確認できますので、併せてご参照頂けますと幸いです。
■ 「玉川上水」とは?
ご承知の通り、玉川上水は、江戸に幕府が開かれてから、急速に人口が増えた江戸の街に、有名なところでは神田上水等により、何とか補っていた水の確保が更に必要になり、江戸時代の初め、東京の西にある羽村から多摩川の水を江戸市中に引き込むために作られた人口の用水路です。そんな玉川上水に関連する逸話的な話は色々とあると思います。いくつか記載させて頂きますと以下の感じになる理解です。
- 高井戸以降は、基本「長い暗渠区間」だが、一部流れを見る事も出来る
- 「奇跡の勾配」と言われる上水の勾配
- 「水喰らい土」と呼ばれれる地質
- 江戸の六上水である玉川上水からはいくつもの「分水」がなされ、江戸市中だけなく、「野火止用水」として、現在の埼玉(新座・志木)にも水を供給した(別記事にて、野火止用水の散策情報も記載しています)だけではなく、周囲の様々な地域に水を供給し地域の発展に大きく貢献
- 最終的には「玉川兄弟が私財を投げ打って完成」
- 台地を削り、谷を避け、断層を超え、「流路は創意工夫」をして、江戸まで水を運んだ
- 現在の玉川上水では、「面白スポット」もあり、川をくぐり、鉄道を越える流路がある
上記の様な逸話的な話が思い浮かぶ「玉川上水」、実際に、自身の脚で歩いてみたいと思いませんか? 自然や地形を感じつつ、そして神社仏閣や遺構を拝見しつつ辿る「玉川上水沿いの散策は、正に大人散策」。多摩川から取水する「羽村堰」~「新宿御苑」まで、40 ㎞ 以上あるので、1日で巡る事は難しいかもしれませんが、分割作戦で行けば、完歩できると思います。別記事では、そのルートやスポットをGoogle My Map で作成した地図と共に紹介しておりますので、是非参考になさってみてください。
【以下「玉川上水」関連記事】






■ 「野火止用水」とは?
「野火止用水」は、東京の立川で「玉川上水より分水」し、小平・清瀬/東久留米の境を流れ、埼玉に入り、新座・志木を流れる(ていた)、江戸時代に作られた人口の用水路」と理解しています。Wikipedia の力を借りますと、以下の様にあります。
野火止用水(のびどめようすい)は 、東京都立川市の玉川上水(小平監視所)から埼玉県新座市を通り新河岸川(志木市)に続く用水路である。 別名を伊豆殿堀(いずどのぼり)という。 かつてはいろは樋を渡って、旧宗岡村にも水を送っており、いろは通りの歩道側には暗渠が現在も残ってる (略) 承応2年(1653年)、幕府老中で上水道工事を取り仕切っていた川越藩主松平信綱は、多摩川の水を羽村から武蔵野台地を通す玉川上水を開削した (略)
玉川上水から領内の野火止(新座市)への分水が許され、承応4年(1655年)に家臣の安松金右衛門と小畠助左衛門に補佐を命じ、野火止用水を作らせた。工期は40日、約24kmを掘り切った。費用は3000両だった。玉川上水7、野火止用水3の割合で分水した。主に飲料水や生活用水として利用され、後に田用水としても利用されるようになった。(略) 野火止用水の開削によって人々の生活が豊かになったことを信綱に感謝し、野火止用水を信綱の官途名乗りである「伊豆守」にあやかって伊豆殿堀と呼ぶようになった (略)
「玉川上水」沿いもそうですが、「野火止用水」沿いも散策している際、目に付くのは、田んぼと言うより「畑」。小平市の直ぐ近くには、田無市と言う市がある事はご存じだと思いますが、この地名は、「田んぼが無いから、田無」となったと聞いた事があります。そんな「野火止用水」も、現在では自然も楽しみつつ散策できる「大人散策スポット」だと思っており、『玉川上水に近いエリアの「緑地帯」』、『住宅街でホタルが見れるらしい「ホタルの里」』、『9本の道が分岐していた事からその名のついた「九道の辻」』、『新緑も紅葉も美しい「平林寺」とその周辺(平林寺掘り・野火止緑道)』等、自然を感じつつも日本の歴史を感じる事が出来ます。2日あれば、完歩できると思いますので、皆様もチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
【以下「野火止用水」関連記事】
■ 「野川」とは?(国分寺崖線とセットで)
「野川」に関しては、別記事で、『国分寺東部から世田谷の二子玉川まで、国分寺崖線にほぼ沿って流れる、20㎞位の長さの川だが、その流路は、人の生活の営みの中で変遷してきた歴史を持つ。古多摩川によってつくられた「国分寺崖線」より、湧水を集めた川であり、旧石器時代の遺構も近くで見つけられ、奈良時代には、その上流部付近に武蔵国分寺が建てられたことからも、人の営みが非常に長い年月にわたって行われてきた痕跡を随所に見る事が出来る地域を流れる川』と言う理解をさせて頂きました。
そして、この「野川」を語る際、セットで抑えるべきなのが、「国分寺崖線」だと、勝手に理解しております。故に「国分寺崖線」についても抑えると、『武蔵野台地(特に東京都内)は、「武蔵野面」と「立川面」の大きく分けて2種類の河岸段丘が見られ、この2つを分ける崖が「国分寺崖線」で、この地方の方言でこの崖を「ハケ」と呼ぶ』と言った理解をしております。
つまり、併せて理解するなら、『武蔵野台地の「武蔵野面」と「立川面」を分ける崖が「国分寺崖線(=ハケ)」で、この「国分寺崖線(=ハケ)」に沿う様に、国分寺から二子玉川まで流れる川が「野川」』という事になる理解です。「野川」だけを歩くのであれば、1日で行けるかもしれませんが、「野川」を大人散策する際は、「国分寺崖線(=ハケ)」とセットで、「崖(=ハケ)」を上下に移動しつつ、「深大寺」・「武蔵国分寺(跡)」等も含め、「河川・地形・神社仏閣等も含めた散策」すべきだと思うので、2日かけて大人散策を楽しむべきだと思っております!
【以下「野川・国分寺崖線」関連記事】
■ 「新河岸川」ってどんな川?
皆様は、「新河岸川」ってご存じでしょうか? 埼玉川越居住の方や東武東上線沿線にお住いの方なら、多くの方が、名前はご存じでしょうが、一般的には、あまり知られていないのでないかと思っております。
『「新河岸川」は、現在では上流部が「赤間川」と言われ、元は、入間市内の「笹井堰にて入間川より取水している用水路」で、この流れが、川越市上野田町付近で「新河岸川」と名を改め流れていき、桜の季節には、美しい桜を拝見できる「川越氷川神社の北側」を抜け、不老川・砂堀川や柳瀬川等と合流し、東京に入って北区にある岩淵水門から荒川の分流を受け、「隅田川」と名称を変えたのち、東京湾に注いで行く川で、江戸期には「舟運」で有名であった川でもある』と言った理解をしており、個人的には、以下の連想をしてしまいます。
- 川越氷川神社北にある「新河岸川の桜並木」を船で下る様は美しいの一言
- 上記の場所は、アニメ「月がきれい」の舞台にもなった
- 隅田川の上流にあたる川が新河岸川で、入間川・多摩川・利根川・荒川等の水が混ざって隅田川となる
- 江戸期は、舟運で有名だった
- 赤間川(新河岸川の上流部分)⇒新河岸川の流れに沿って散策するとこの地域の文化や歴史を感じられる
特に、現在「赤間川」と呼ばれる上流部は、「これって本当に新河岸川に繋がるの?」、「ただの用水路だよね…」と思ってしまうでしょうし、川越市民の方でも「菓子屋横丁付近より上流は、玉川上水・野火止用水・野川みたいに散策路も整備されていないので、よくわからない…」と言った感じだと思います。故に、ローカル色の強い表現で恐縮ですが、「こんな普通の用水路が、新河岸川・隅田川になって東京湾に注いでいく川になる過程を、新河岸川沿いの大人散策スポットと共に巡るのは正に大人散策なんです!」とお伝えしたと思う次第です…。是非、川越付近にお住まいの方には、おすすめしたいと思います。
【以下「新河岸川」関連記事】
【最後に】
以上が、「別記事で紹介しております、『玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川』等の流れに沿って実行した『水辺の大人散策』情報に付き取りまとめ」をさせて頂きます(各リンクより、それぞれの概要と、具体的なルートや各スポットを記載した大人散策Map(Google My Map にて作成)と共に紹介しておりますので、併せてご参照ください)。
個人的には、中々ニッチな分野で、「玉川上水・野火止用水・野川・新河岸川を流れに沿って歩いてみよう!」と思う方は少数派だと思います。ただ、逆の言い方をすれば、「それぞれの地域で、生きてきた先達の方々の生活の痕跡」を感じる事が出来る散策だと思う次第です。先にも記載しましたが、「人は水が無いと生きていけません」ので、「その水を確保すべく、我々の先輩たちが築いた遺構」を感じるべく、「水辺の大人散策」を実行してみてはいかがでしょうか?
【あわせてお読み頂きたい! 「水辺の大人散策シリーズ」の関連記事…】