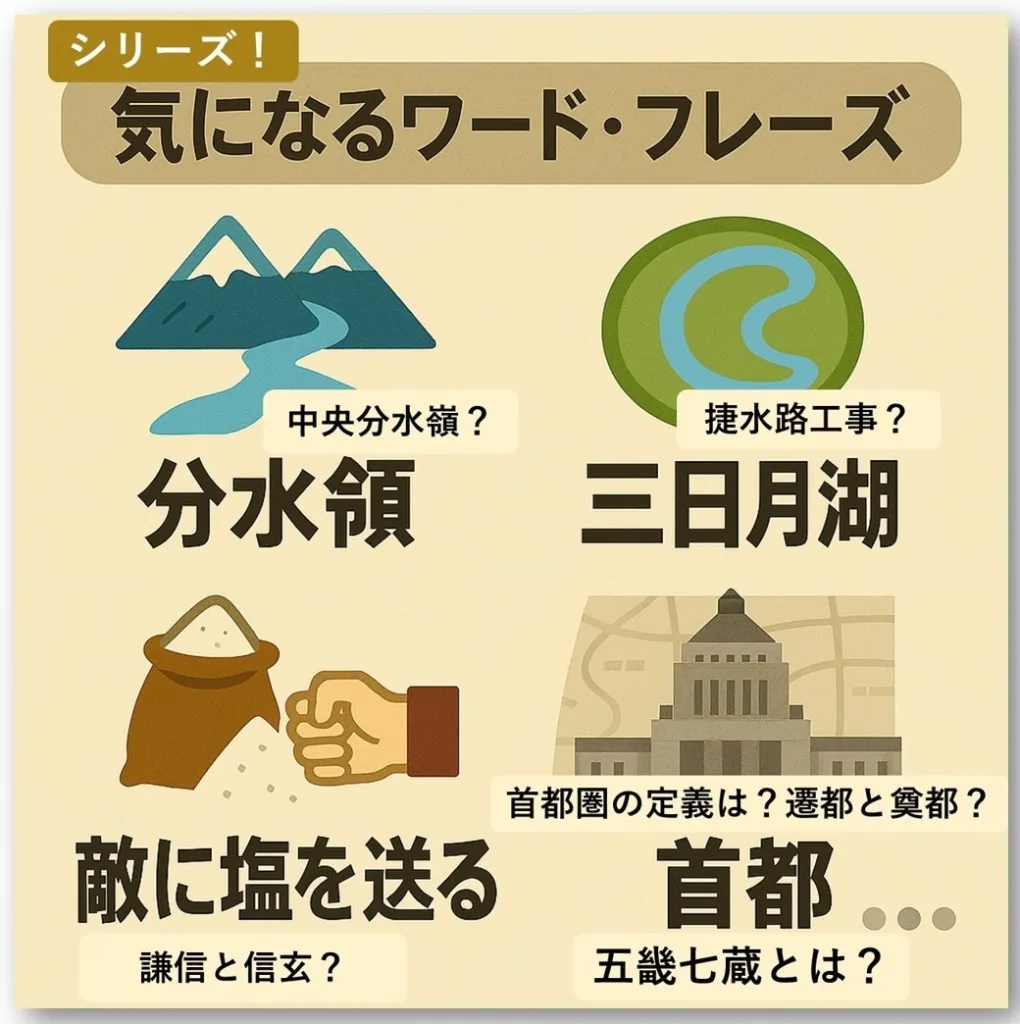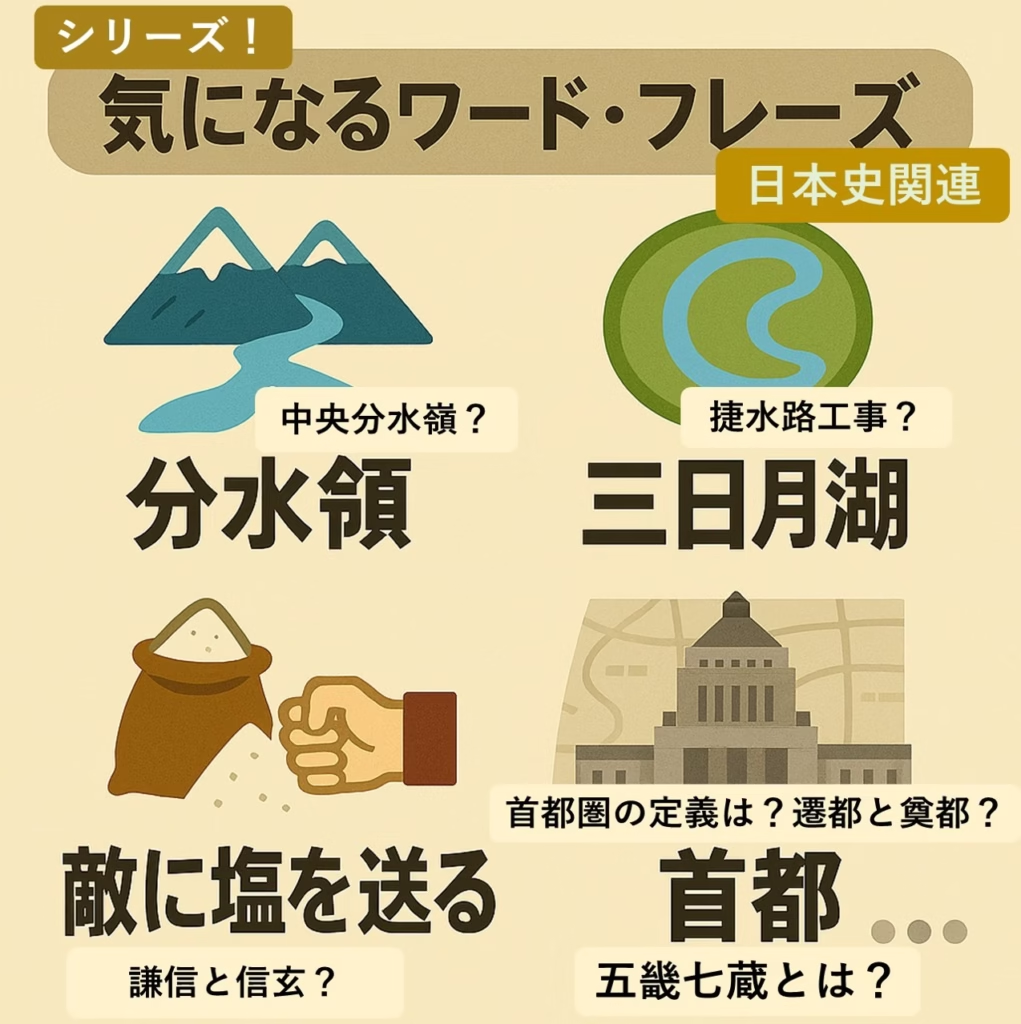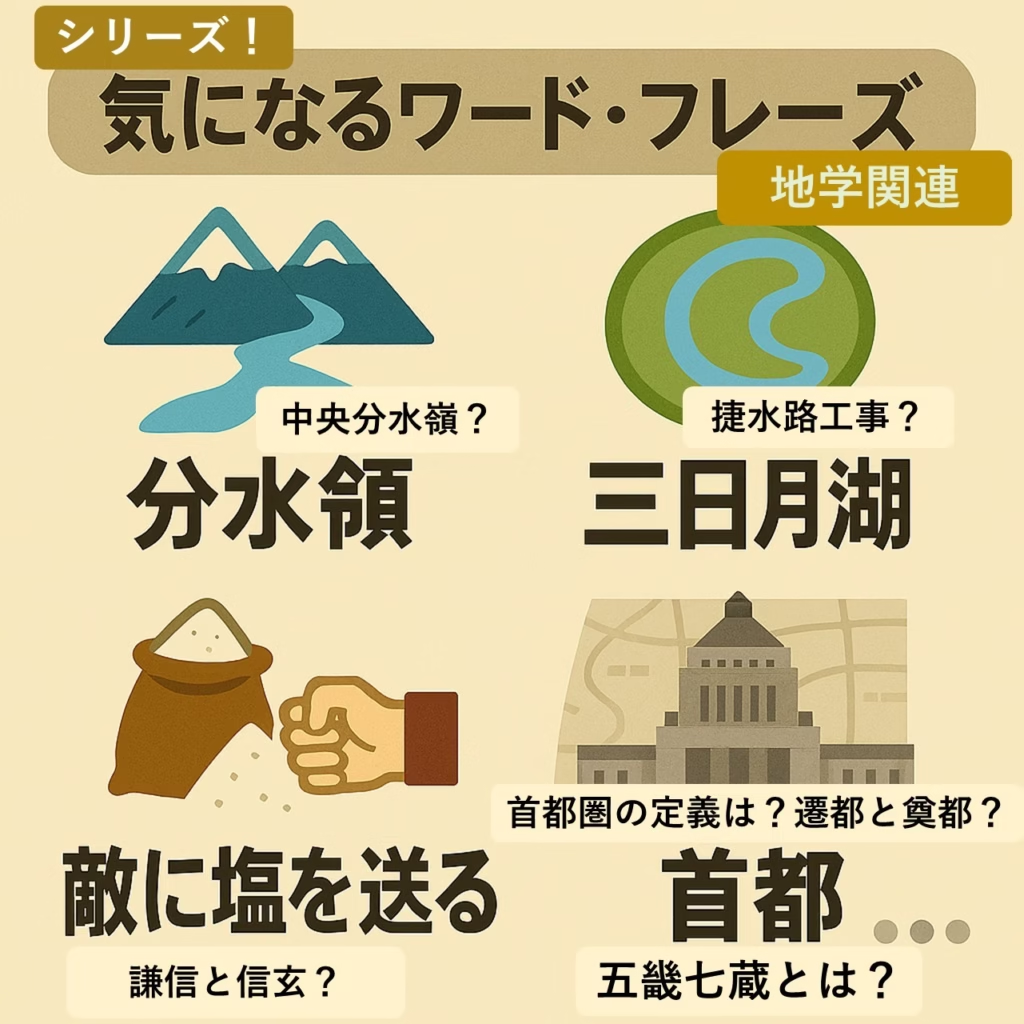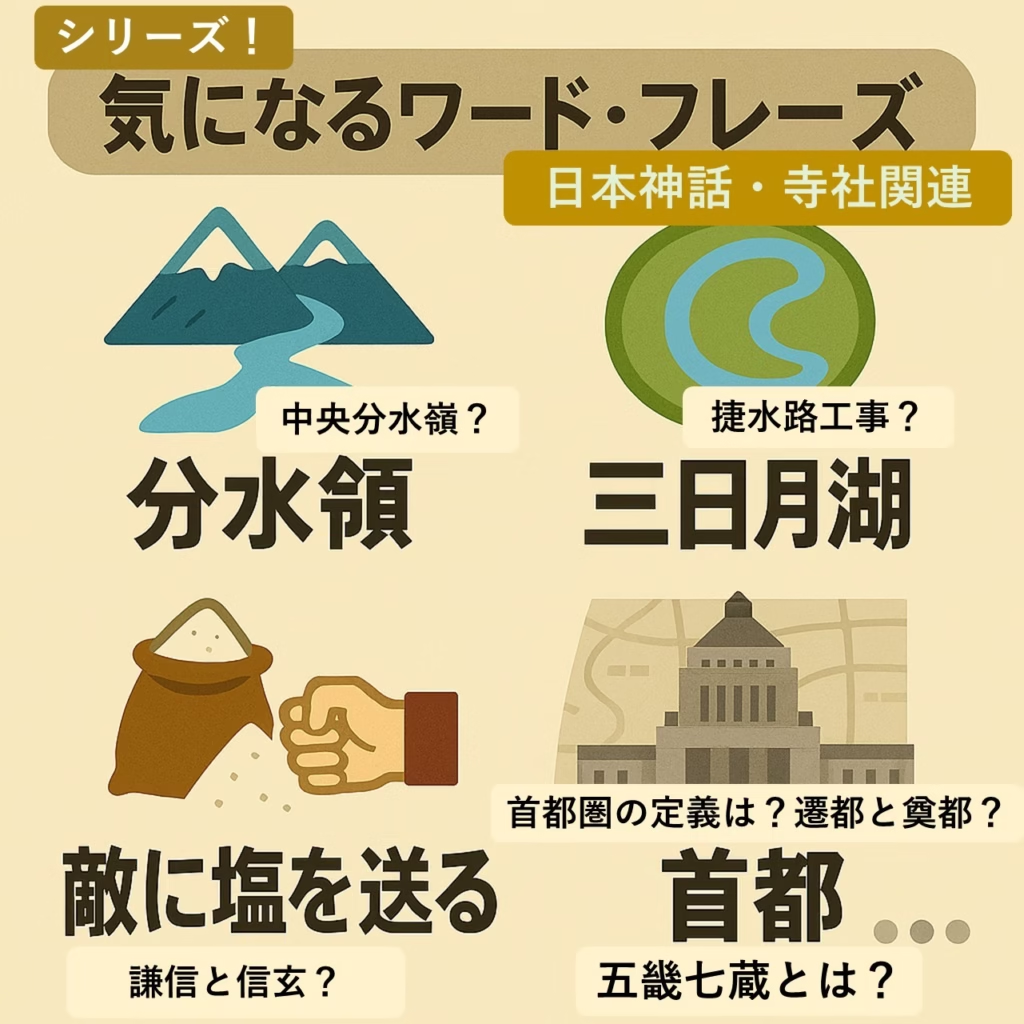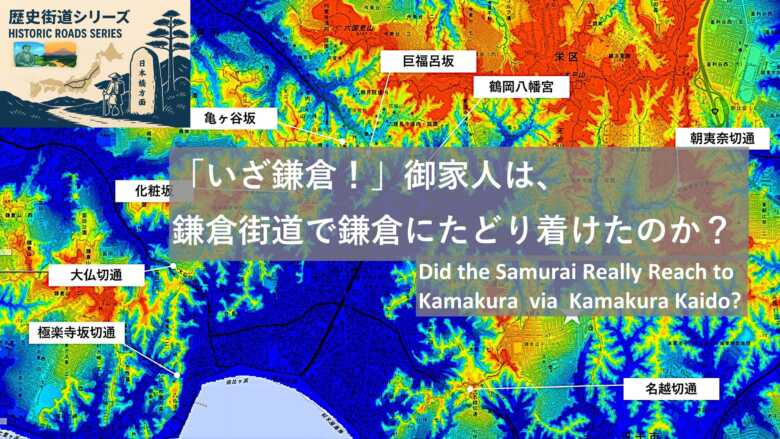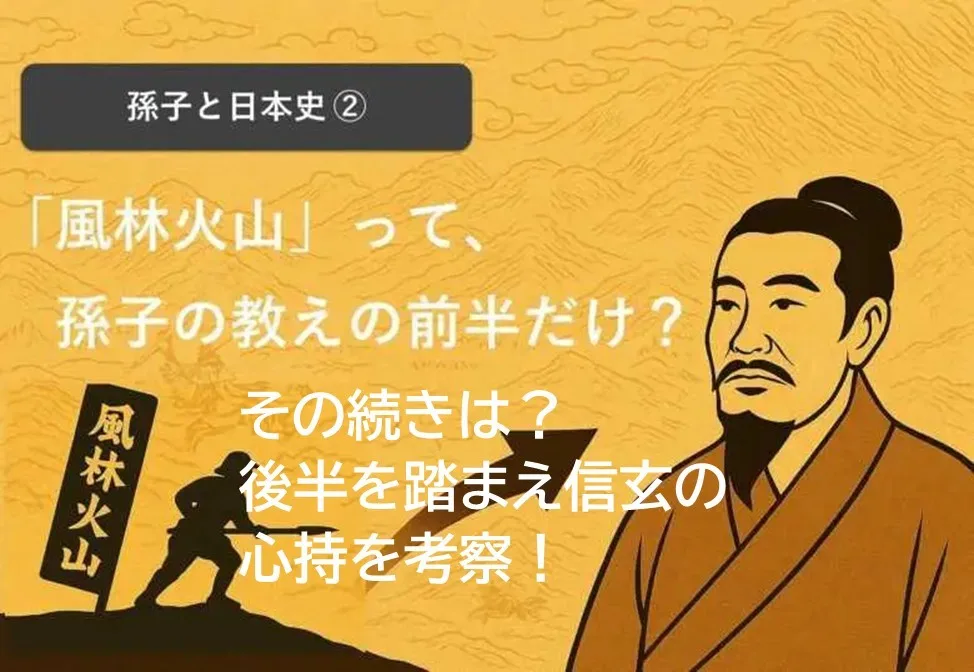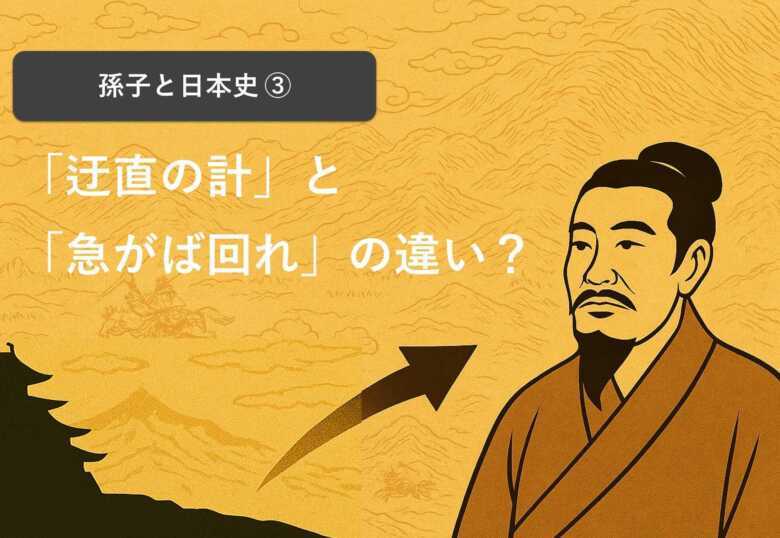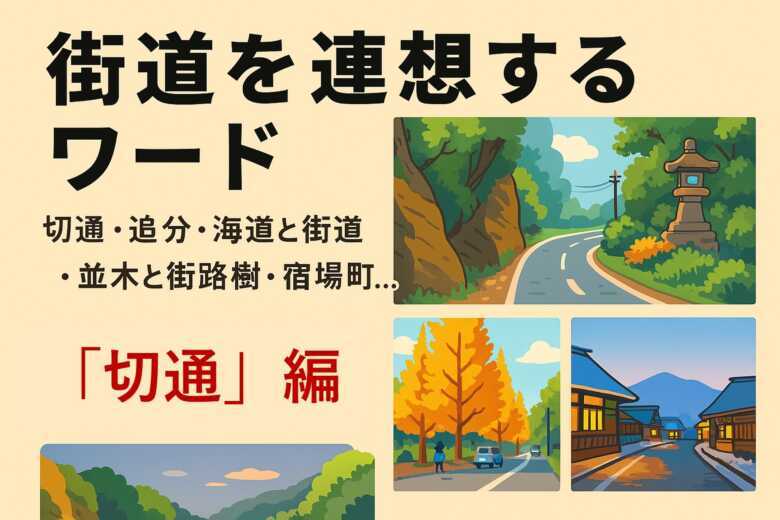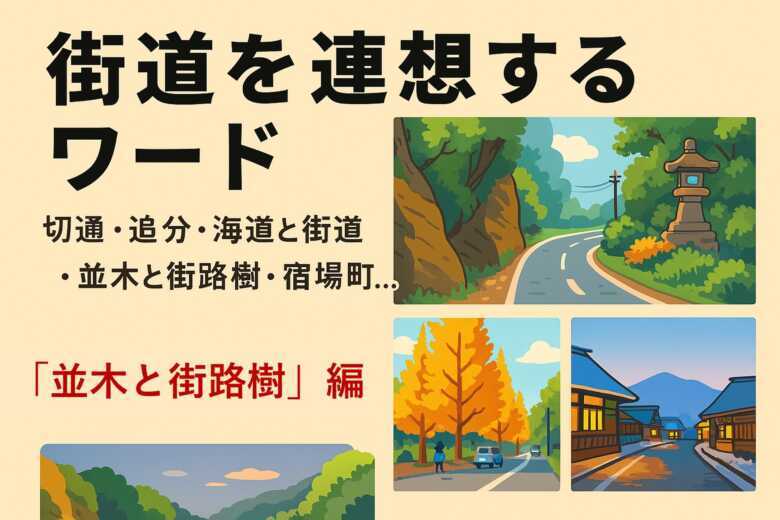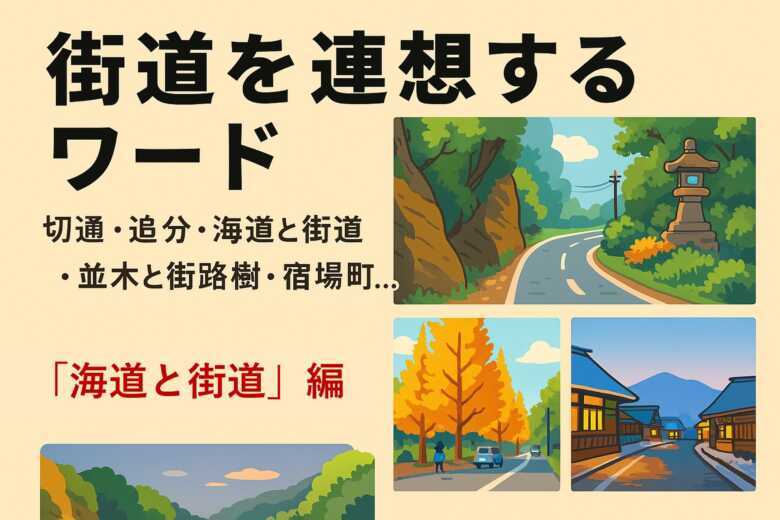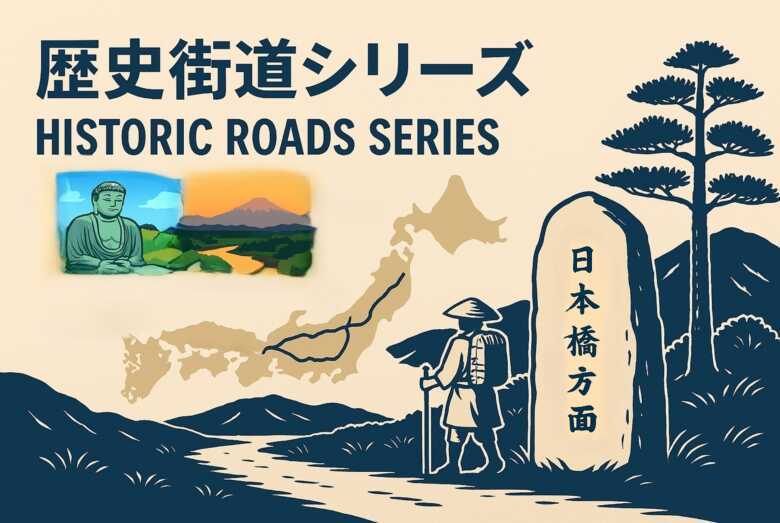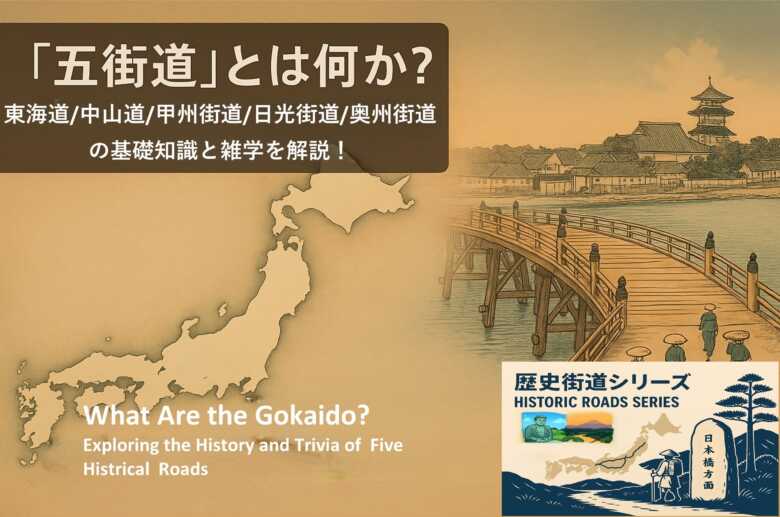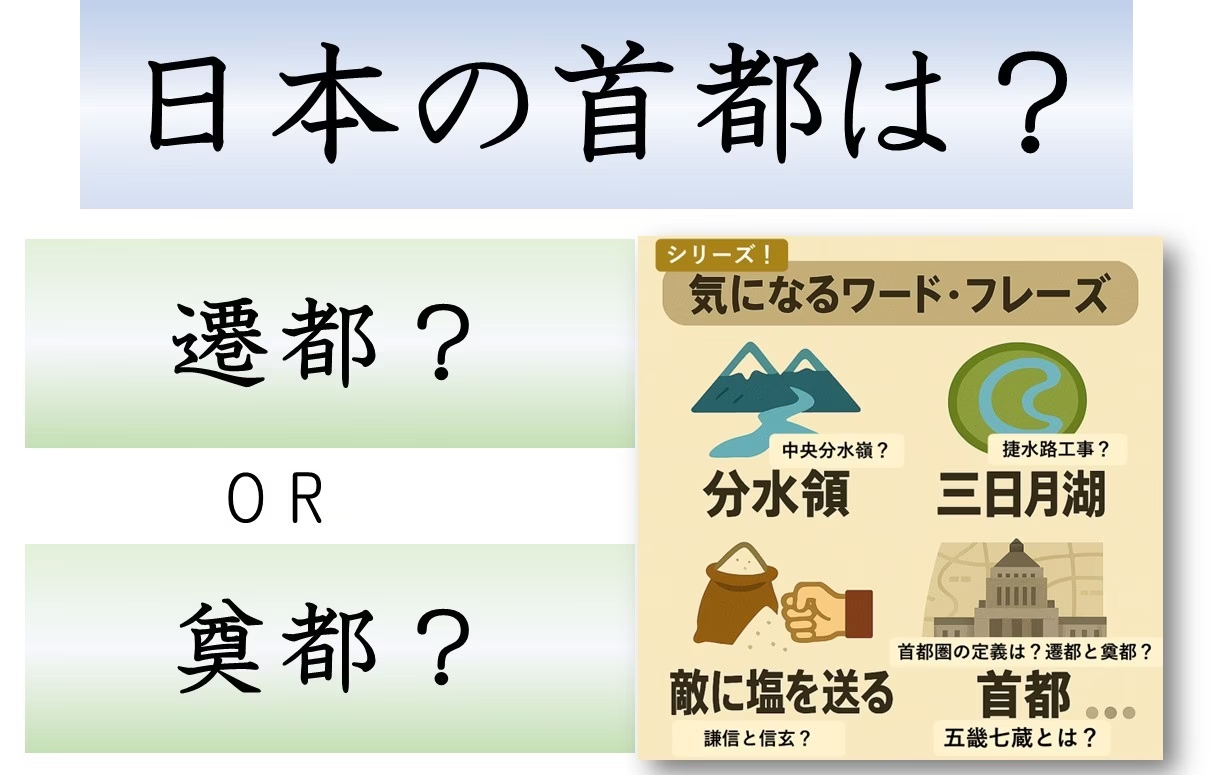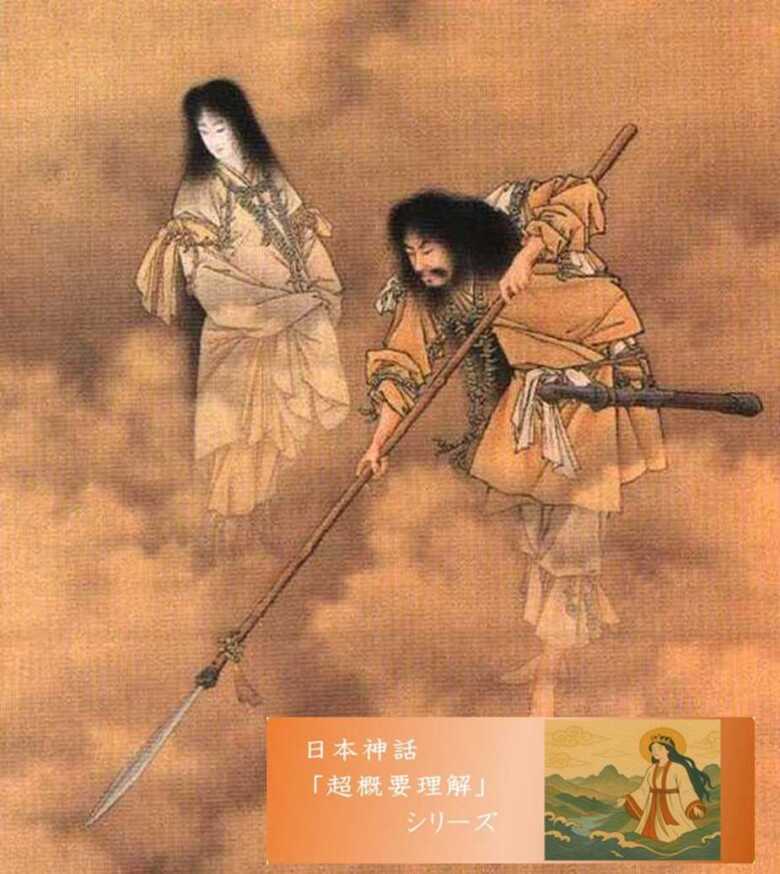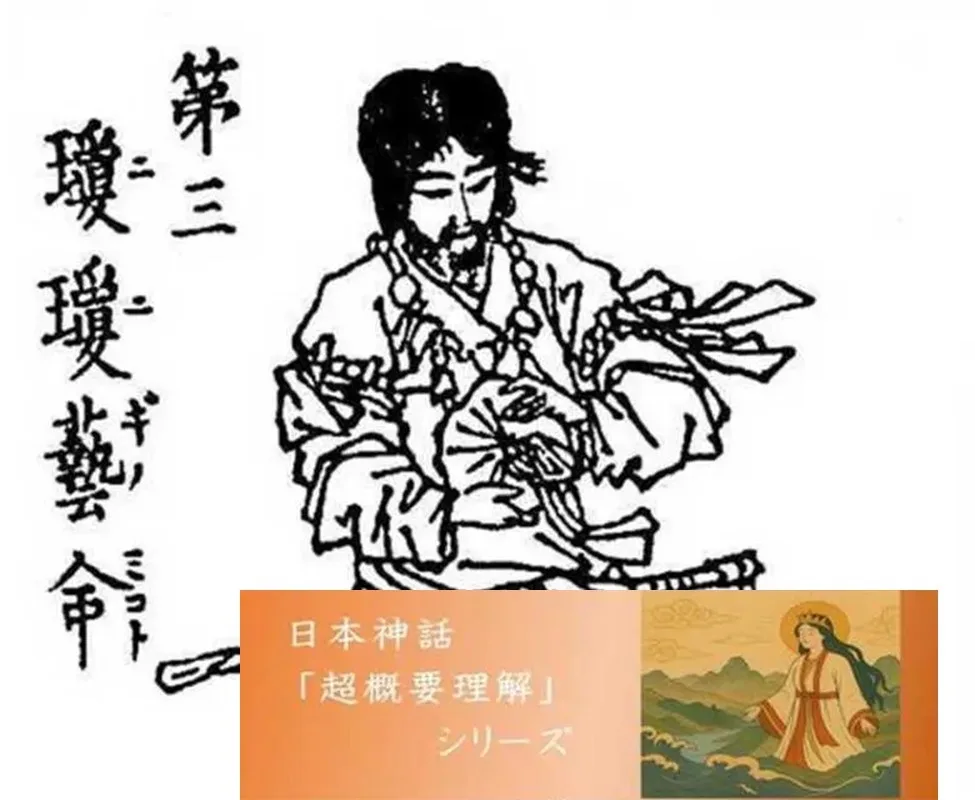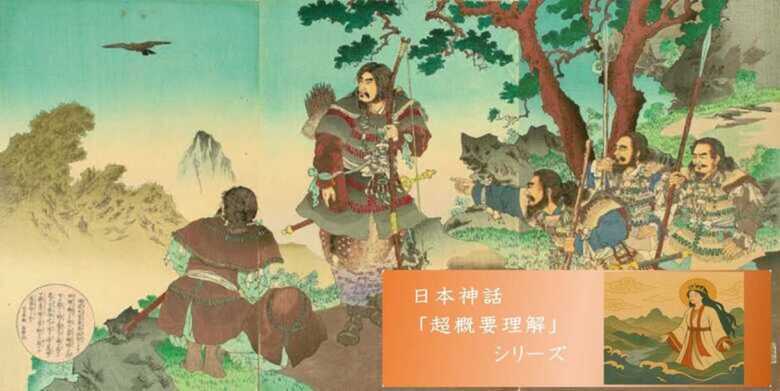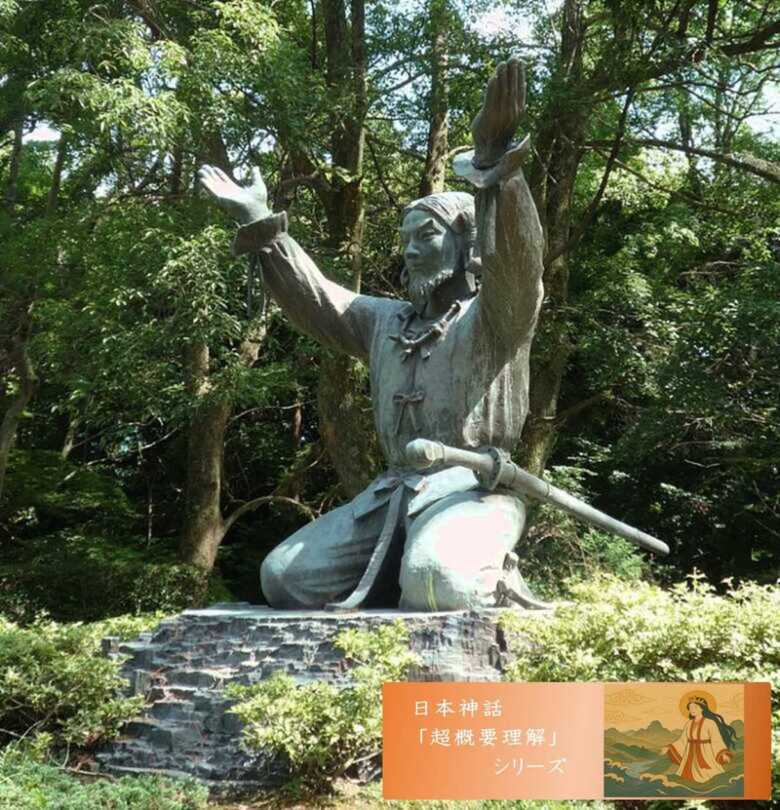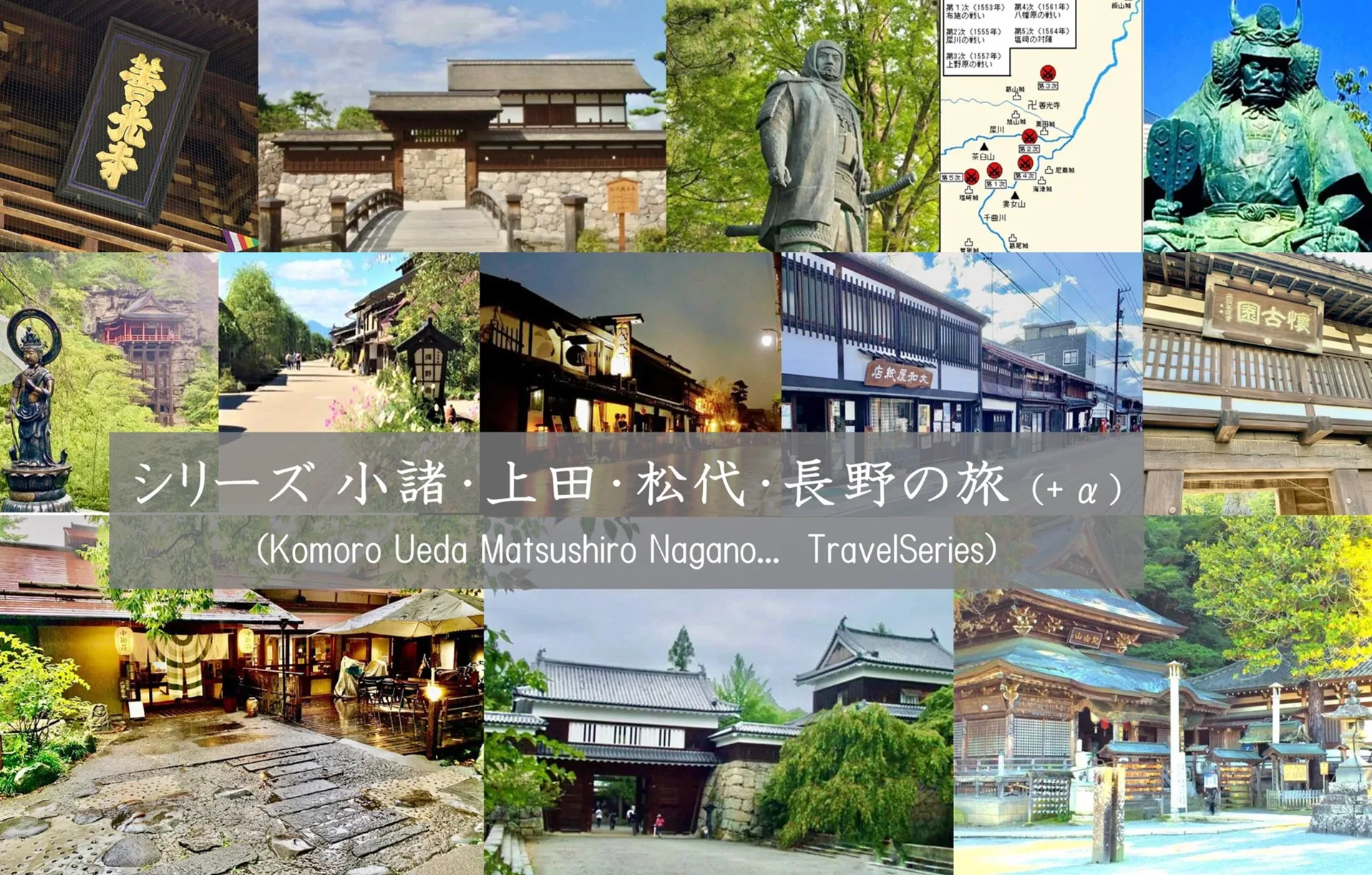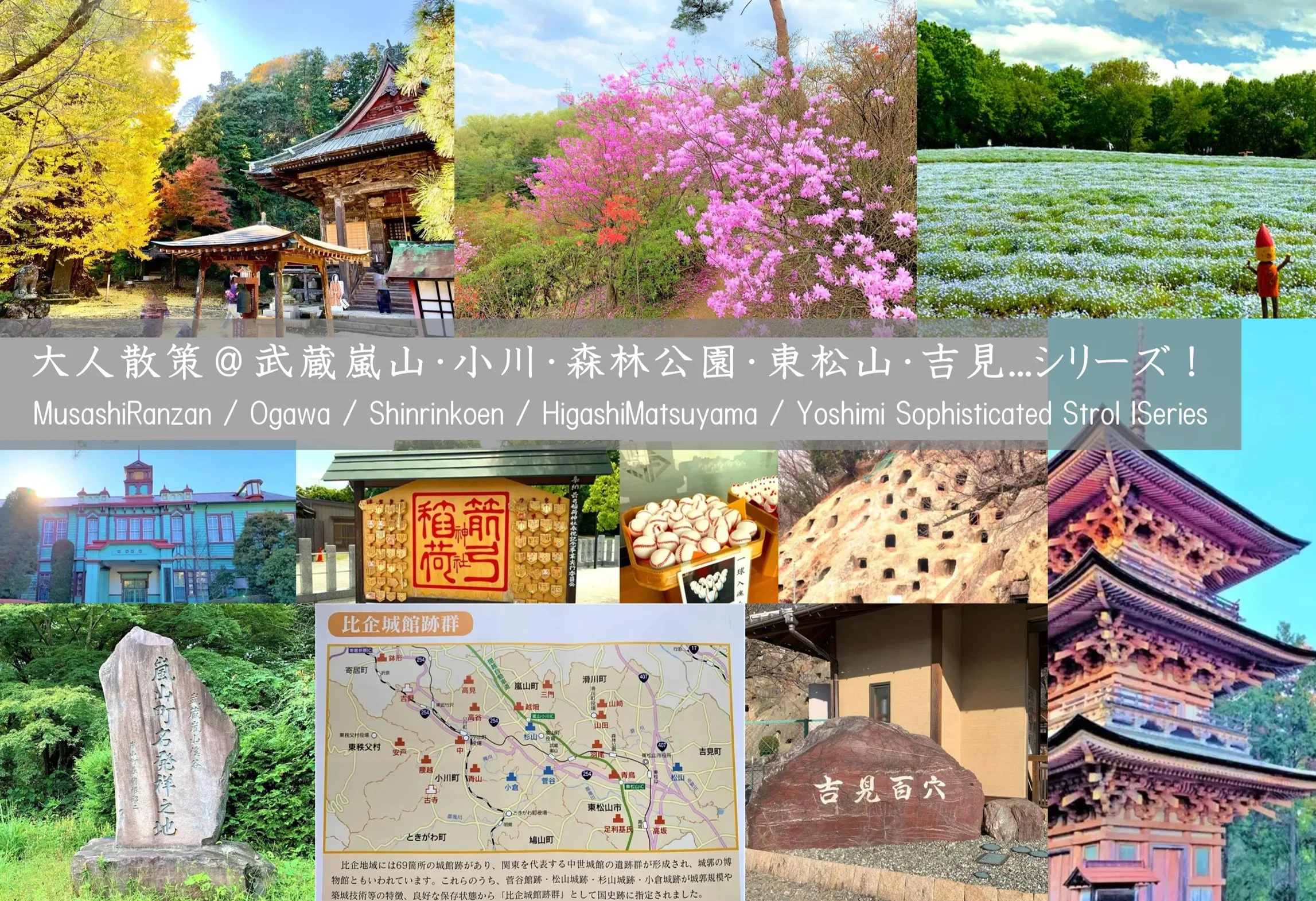日本の首都は法的に決まっている?
現行法令に「首都」の定義はなく、東京=首都は“慣習的認識”に基づくものです。
京都から東京への移行は遷都?
明治期には「遷都」と明言されず、「奠都」という表現が使われました。
東京が首都と“公に”扱われ始めたのは?
1943年に「東京都」が成立したことが大きな転換点と理解します。
京都は今も「都」と言える?
文化的中心としての京都は、歴史的に「都」と呼ぶにふさわしい存在と理解します。
「首都は東京、都は京都」という整理は妥当?
政治の中心=東京、文化の中心=京都という理解は歴史的経緯に沿っている認識です。
【はじめに:
「日本の首都」の定義は?】
こちらのページでは、「『日本の都は “京都”、首都は “東京”』と言われる様になった、その『背景や歴史』に付き考察」を加えてみたいと思います。
📚本記事で得られる情報📚
✅「日本の首都」の定義・その歴史
✅「遷都」と「奠都」の違い
✅「東京」と「京都」を「首都・都」の視点で考察
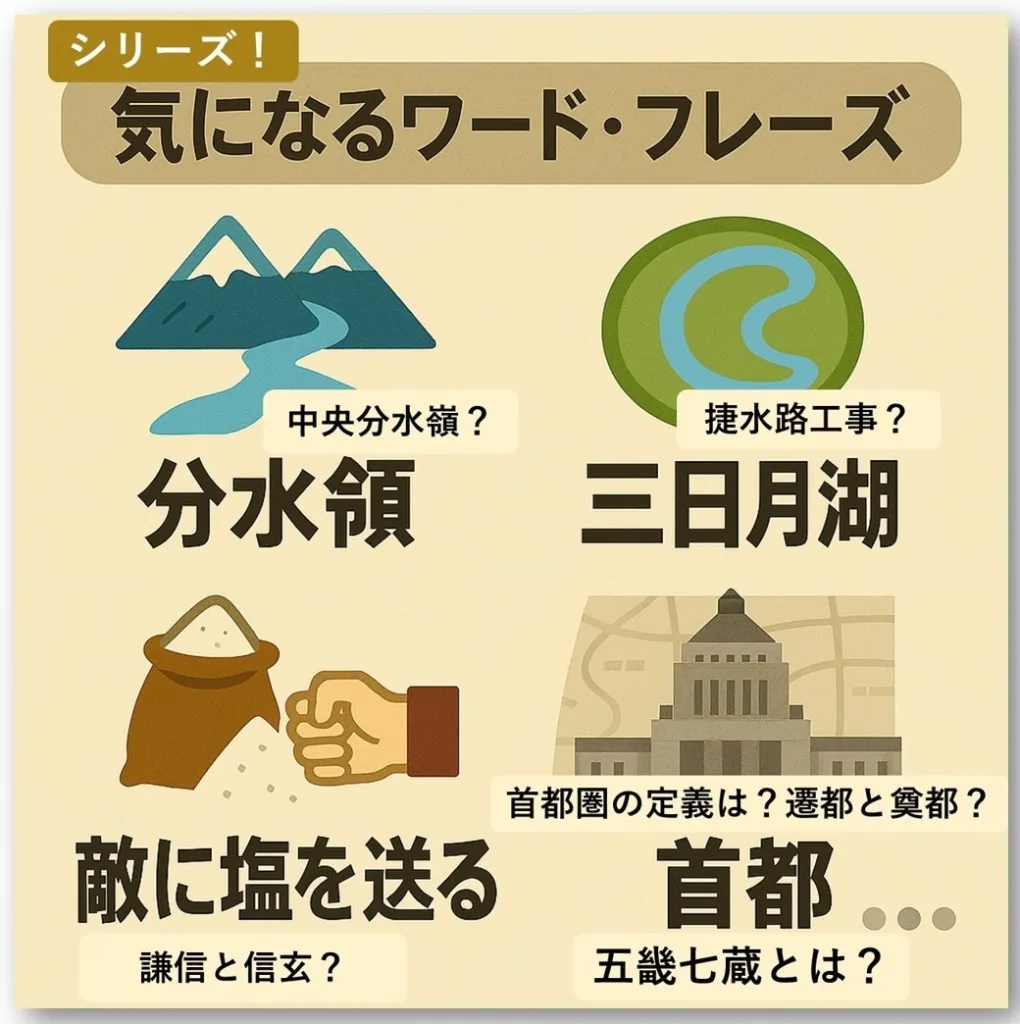
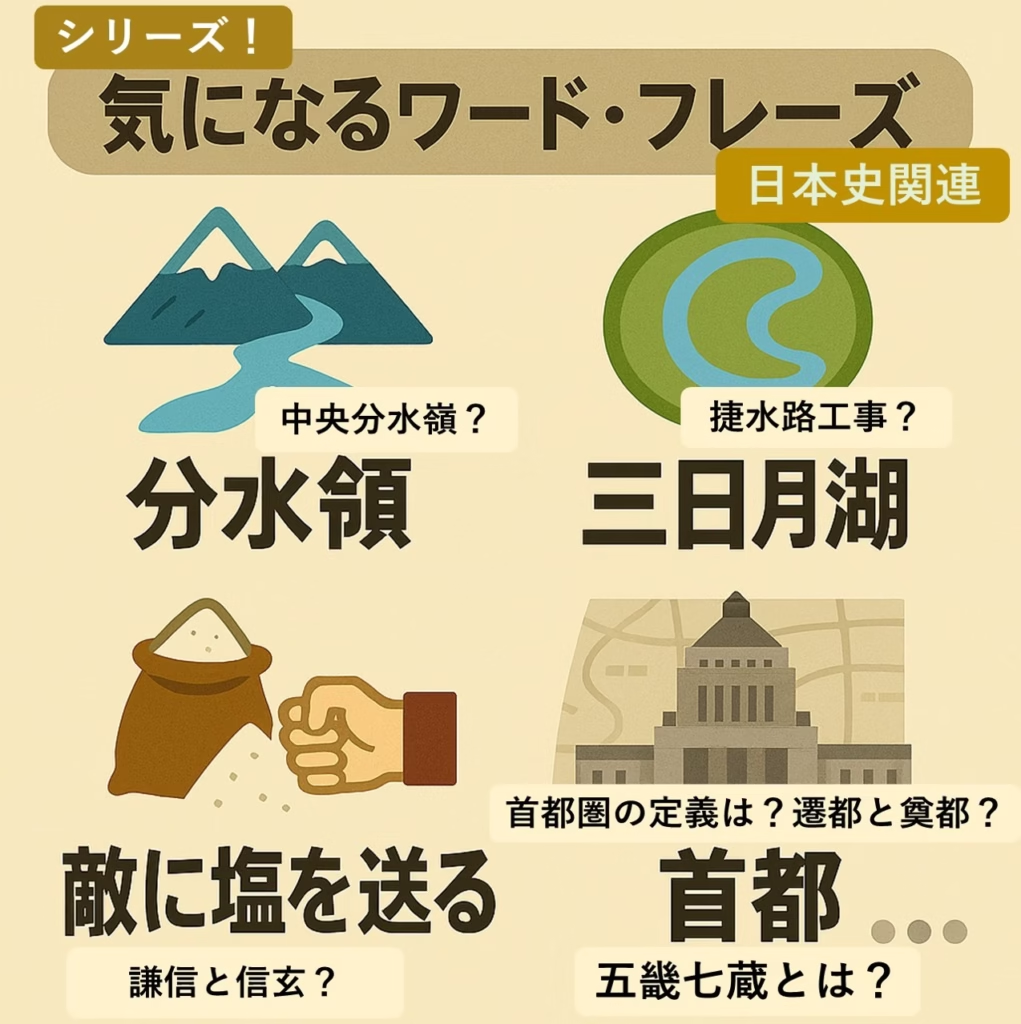
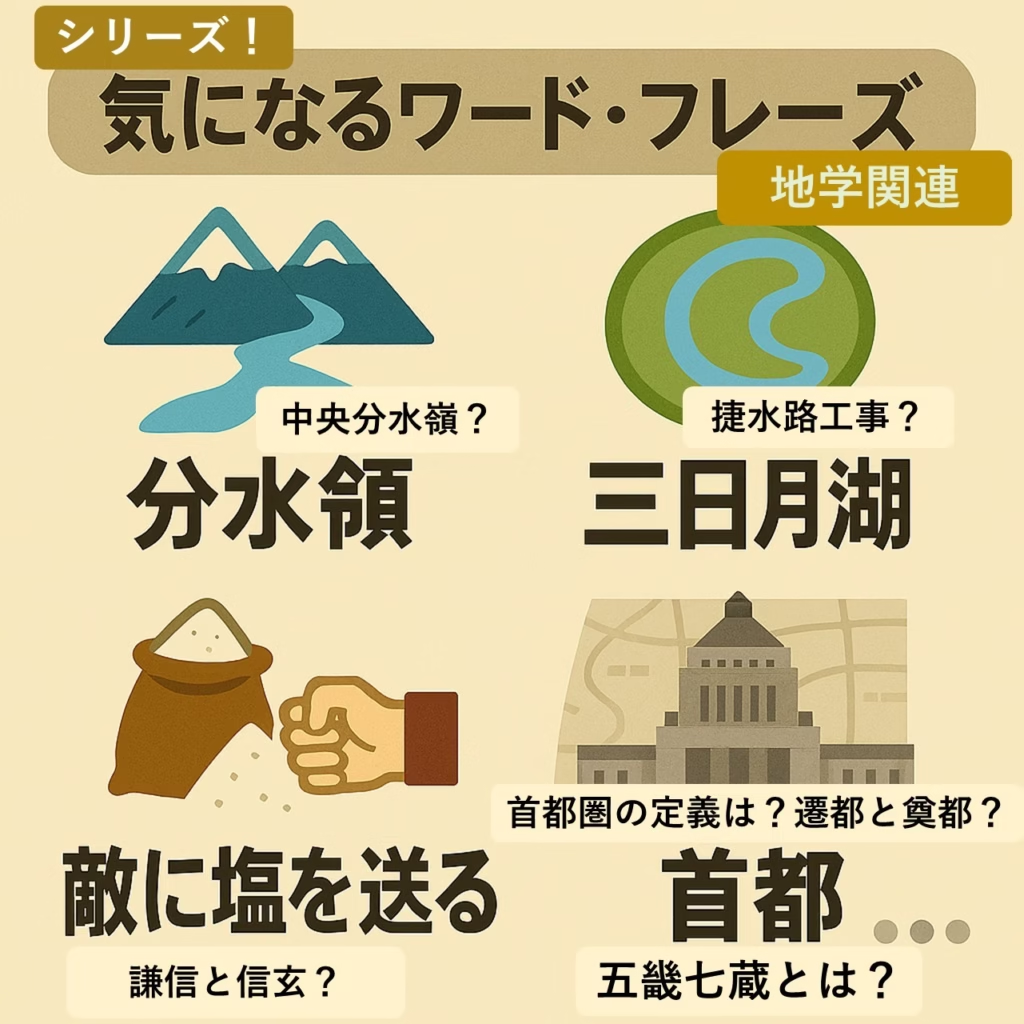
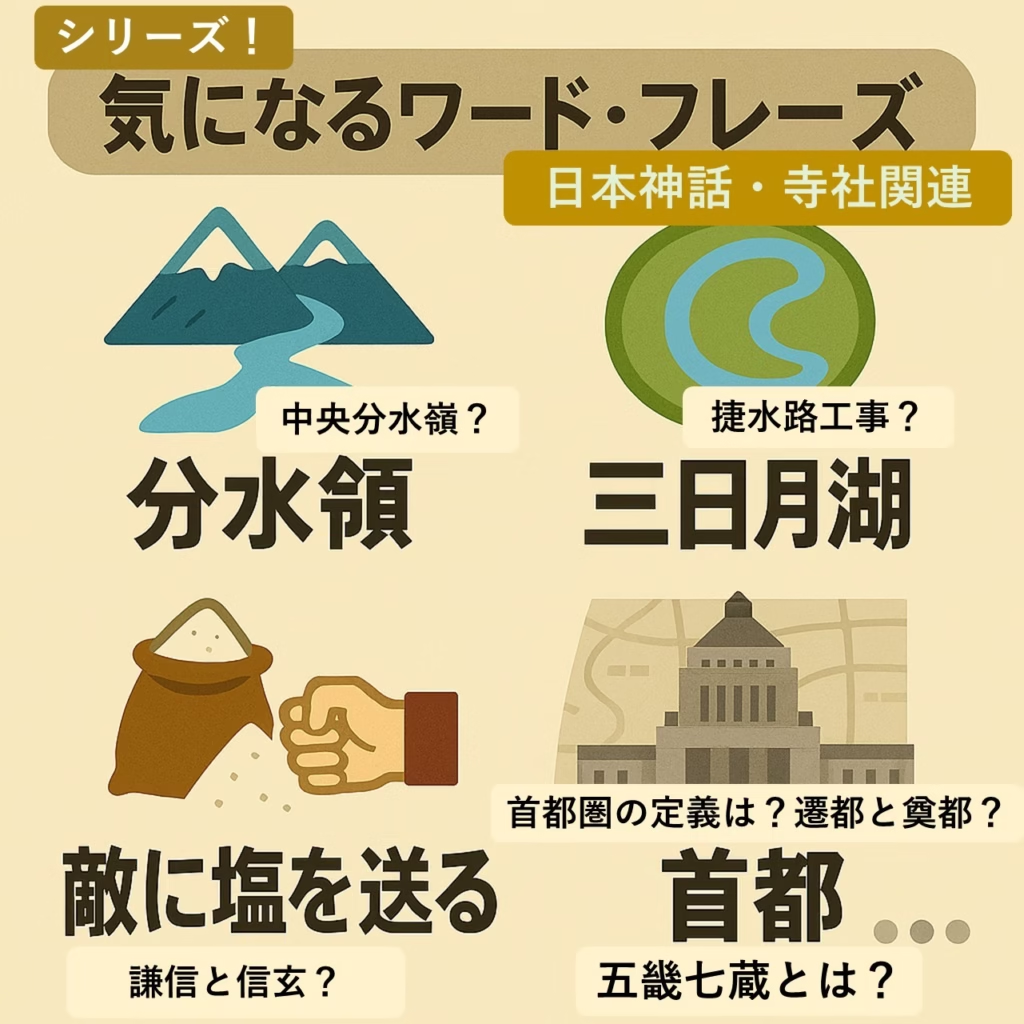

故に、まずは皆様にお伺いします…。「日本の首都は何処?」でしょうか??? とは言ってみたものの、「日本の首都は “東京”」ですよね…。しかしそのより所は、何処にあるのでしょうか? 「”なぜ” 東京が首都」なのでしょうか? こう聞かれてしまうと、答えに困ってしまう部分もあると思います。そもそも、「首都の意味」を、Wikipedia の力を借り、調べてみますと、以下の様にあります。



-.jpg)


首都(しゅと、英: capital / capital city)とは、一国の中心となる都市のことを指す。ほとんどの場合にはその国の中央政府が所在し、国家元首等の国の最高指導者が拠点とする都市のことである。ただ、場合によっては、中央政府の所在とは別に、その国のシンボル的存在として認められている都市が首都とされることもある (略)
https://ja.wikipedia.org/wiki/首都
確かに…、東京には「中央政府・天皇の在所」があるので、「日本の首都は ”東京” 」で、間違いえないの様です。しかし、文章中に「ただ、場合によっては・・・」の文面があるので、同じく、Wikipedia の力を借り、「日本の首都」を調べてみますと、以下の様にあります。






(略) 現在、日本の「首都」は、一般的に東京都と認識されている。日本の現行法令には「首都圏」の定義は存在するが(首都圏整備法)「首都」についての定義はなく、また過去においても「首都」という明治以前には一般的でなかった語と伝統的な用語である「都」「京」との関係について明確にされたことがなく、「日本の首都」という語そのものについて議論がある。日本の法令で初めて「首都」の語を用いたのは1950年に制定された「首都建設法」(昭和25年法律第219号)だが、同法は1956年に廃止されており、現行の法令で「首都」について直接的な表現を用いて定めるものはない。同法の第12条には「東京都が国の首都であることにかんがみて」とあり、東京都が首都であると明記されていた (略)
(https://ja.wikipedia.org/wiki/日本の首都)
つまり、『日本の首都は、明確に定義されていないが、状況的に考え「日本の首都は東京だ!」と皆がそう思っているので、日本の首都は東京』と言う事らしいです…。







【「京都から東京へ」は「遷都」ではなく「奠都」?】
そんな、「定義はないが、一般共通認識として認められている首都・東京」ですが、歴史を少しさかのぼってみます。
江戸時代の「日本の都」は「京都」ですよね…。これは、江戸幕府があったように「東京(=江戸)に、政治の中心はあった」が、「天皇の在所が京都」であった為、「日本の首都は京都」と言われている認識です。794年から江戸時代が終わるまでの1000年強、「日本の首都(=都)は、一般的に京都」と認識されていた訳です。








しかし、明治に入り、天皇の江戸への2度の行幸の後、天皇の在所が、事実上「江戸」となり、「京都に対し、東の京」と言う意味で「東京」と名付けられ、「東京が、日本の首都になった」と言う理解が一般的である認識です。しかしこの時、「都を江戸に移す」とは、誰も明言していない様で、言葉も「遷都(=首都を移す)」ではなく「奠都(=都を定める)」と言う言葉を使ってきたようです。
また、「東京となってからしばらくは、日本には『京都と東京の2つの都』がある」と言う、考え方もかなり根強くあったようです。言い換えれば、『東京を都と定めた(奠都)だけであって、京都から東京に都を移した訳ではないが、事実上の「遷都」に変わりない』と言う理解で良い気がしました。
この考え方、立ち振る舞い、なんとも日本人らしい発想だと思いませんか? 「京都の人達に、配慮しつつ、新しい道のりを「玉虫色」に始め、皆の共通認識が分かれるので、完全には一致しないが、大筋での認識は共通のものとなり『事実上、東京が首都』になっていく」訳ですから…。これは、ある意味日本人が海外から非難される事象であると同時に、「日本人の良さの1つ」でもあると思った次第です…。


【東京が首都との認識が “公に” 広まったのは、終戦直前?】
ちなみに、1869年から1943年まで、東京は、東京府と言われていたようで、同時に京都も大阪も府であった様です。Wikipediaにて、「都道府県」を調べてみますと、以下の様にあります。
(略) 1869年9月29日(明治2年8月24日)の太政官布告によって、京都府・東京府・大阪府以外は全て県と称することが決まり、前後して他の府(神奈川府・新潟府・越後府・甲斐府・度会府・奈良府・箱館府・長崎府)が県に名称変更した。この時点では、天皇が東京行幸で東京にいたが、高御座(天皇の在所を示す玉座で、これのある場所が皇居とされる)の移動が無かったので、高御座のある京都府の方が東京府より序列が前になっている。
なお、この太政官布告前は、東京府は江戸府と呼ばれており、同時に江戸から東京に改称された。1871年8月29日(明治4年7月14日)に行われた廃藩置県により、藩は県となって、全国が明治政府の直轄となった。結果的に、1使(開拓使)3府(東京府・京都府・大阪府)302県となる。この時点では江戸時代の藩や天領の境界をほぼそのまま踏襲したものであったため、飛び地が全国各地に見られ、府県行政に支障を来たしていた。同年12月にはこれを整理合併(第1次府県統合)し、1使3府72県となった (略)
https://ja.wikipedia.org/wiki/都道府県


同様に、「東京府」をWikipediaにて調べてみますと、以下の様にあります。
(略) 日本が日中戦争に突入すると戦時体制構築のため、政府は東京府地域の政治・経済の統制強化を要求するようになった。1938年6月、内務省は「東京都制案要綱」を発表したが東京市35区は内務省案反対を決議した。しかし1943年1月、政府が帝国議会に提出した「東京都制案」が可決され同年7月1日、東京都制によって東京府・東京市が廃止されて「東京都」が設置された。旧東京市域は東京都35区となった (略)
https://ja.wikipedia.org/wiki/東京府
つまり、1870年前後の段階で、かなり形は違うが、「今に近い都道府県の形」が出来たものの 「”都” は存在していなかった」が、1943年に、時代背景・政治的な意図の中で、東京都が出来た様です。
時代背景や政治的な意図は、別として、この事実から見ると、私の個人的な理解は、以下の様になりました。
『日本人の考え方の根底に「明治初めには、実際に「東京(皇居)に天皇」がいらっしゃり、行政機関もあったが、まだ「正式な玉座のある京都」や「一時、奠都先に名前が上がり、重要都市であった “大阪“」を府として同列に扱う配慮があった。
しかし時代を経て、状況として「誰もが “東京を首都” と認めるような土壌が出来たタイミング」で、時代背景・政治的意図が重なり、東京府は「都」という概念・文字(都=みやこ)を持ち出し、「東京の首都としての位置づけ」を曖昧ながらも宣言し、終戦の少し前(1943年)に、現在の1都2府になった』
つまり、私の勝手な理解は「東京が誰もが認める首都になったのは『1943年』」と言う事になった次第です。




【最後に:「京都」を「都」と言って良いか?】
以上が、「『日本の都は “京都”、首都は “東京”』と言われる様になった、その『背景や歴史』に付き考察」を申し上げた内容になります。
そんな、曖昧ながらも「世界中から日本の首都として認められている『東京』」が、「都」を名乗る経緯を勝手に考察してみると、少し前の話ですが、前の「日本維新の会」の「大阪『都』構想」は、『政治的意図は理解できるが、「都」と名乗る事を “根底で許してもらえなかった” のでは?』、と思ってしまったのは、私だけでしょうか?(何度かダメでしたし…)
同時に、実際に京都に訪れてみると(別記事で、関東圏から京都への日帰り旅行に付き、記載しています:1回目 + 2回目)、「日本の文化の中心は、やっぱり京都」です! 政治・経済の中心で、天皇のいる「東京が日本の首都」だと認めつつも、「日本が日本である所以の日本文化の中心は京都」だと思ってしまいます。そういった意味では、私としては、今後も東京を正式に首都として定義はせず、このまま、京都も日本の都(みやこ)である事を心の片隅に残しておきたいと思いました。


「首都」と言われると、経済的・政治的な考え方に焦点を置いた中心地を表し、「都」と言われると、文化的な考え方に焦点を置いた中心地を表している感じもするので、
「首都は東京、都は京都」
これが私の最もしっくりくる、「くくり」に思えた次第です。
(関連情報として、北海道は、明治になって五畿七道における流れから、北海道と名付けられ、五畿八道になった件については、別記事で、勝手な考察を紹介しております)
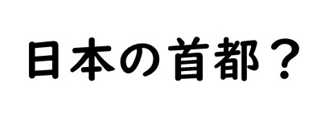
【あわせてお読み頂きたい! 「気になるワード/フレイズシリーズ」の関連記事…】